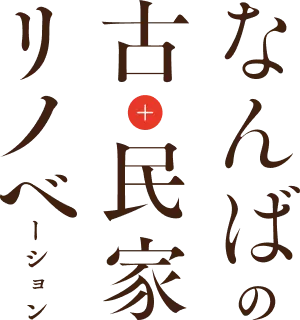「新築かリノベか」迷ったときに読む、後悔しない家づくりの選び方ガイド【前編】

明治20年創業、倉敷市の工務店なんば建築工房では、新築注文住宅から、リノベーションまで、様々な工事に対応しています。
近年、リノベーションの需要が高まるなかで、「新築(建て替え)すべきか、リノベーションを選ぶべきか?」というご相談を受けることが増えてきました。
今回は、同社の代表であり、古民家再生や空き家利活用の分野でも豊富な実績を持つ、正田順也社長に、どちらの選択肢が適しているかを伺いました。

正田 順也 (まさだ じゅんや)
大阪生まれの奈良育ち。大学進学をきっかけに岡山へ移住し、住宅業界歴は30年超。
職人の伝統技術を活かすため、古民家再生・空き家利活用・地域づくりに力を入れている。
(一社)全国古民家再生協会岡山第一支部 代表理事
(一社)全国空き家アドバイザー協議会 岡山県倉敷支部 事務局長
町おこし団体 下津井シービレッジプロジェクト 事務局長
古民家鑑定士インストラクター ほか
よくある3つの相談パターン

――新築かリノベーションかで悩む方には、どのようなパターンが多いですか?
正田「お客様の相談内容としては、大きく3つのパターンがあります」
①現在お住まいの家が古くなってきて、建て替えるのか、リノベーションするのか悩んでいる
②親御さんやご親族から古い家を受け継いで、解体して新築するか、活用するのか悩んでいる
③新築を建てるのか、中古物件を購入してリノベーションするか悩んでいる
正田「どのパターンにも共通して言えることですが、まずは建物の状態による、ということです。建物の状態が非常に悪くなければ、リノベーションの選択肢が入ってくると思います。特に、雨漏り、家の傾き、シロアリ被害といった、家の重要な構造が傷んでいる場合は、高額な費用がかかる場合もあります。他にも、家の規模や、周辺環境、さらには法的なリスクや将来の家族計画なども踏まえて総合的に判断する必要があり、一口にこうした方が良い、という答えはありません」
新築のメリット・デメリット

正田「新築を選ぶ最大のメリットは、自由な間取り設計が可能なことです。敷地の形状や暮らし方に合わせてゼロから設計でき、断熱・耐震などの性能面でも最新基準に対応しやすくなります。一方で、デメリットとしては、リノベーションに比べると割高になりやすかったり、建て替えの場合は解体前と同じ規模の家を建てることが法的に難しい場合もあります」
◆新築のメリット
- 間取りの自由度が高い
- 耐震・断熱性能が担保しやすい
◆新築のデメリット
- (建て替えの場合)解体から建築までの費用がかさみ、割高になりやすい
- 固定資産税が高くなる場合がある
- セットバックが必要になったり、現状と同じ場所に建てられない場合も
正田「また、古民家や親の代から受け継いだ建物など、“家に宿る思い”を引き継ぐことができない点に寂しさを感じる方もいます」
リノベーションのメリット・デメリット

正田「リノベーションの最大の魅力は、建物に込められた“思い”や“歴史”を残しながら、現代の暮らしに合わせて住まいを整えられることです。また、一般的には新築よりもコストを抑えられるケースが多いですね」
◆リノベのメリット
- 新築よりコストが7~8割に収まることが多い
- 固定資産税が上がりにくい
- 古い家の素材や雰囲気を活かせる
- 家族の思い出を引き継ぐことができる
◆リノベのデメリット
- 間取りに制約がある(構造上、位置が変えられない)
- 駐車場が確保できないなど、敷地利用に限界がある場合も
- 断熱・耐震性能の確保には、経験のある工務店の判断が必要
正田「リノベーションは、“何を残し、何を変えるか”の判断がとても重要です。だからこそ、ただ直すだけでなく、減築や建物整理などを含めた“全体最適”の視点で提案することを心がけています」
意外に差が出る、固定資産税の違い
――実際のところ、固定資産税はどのくらい変わるのでしょうか。
正田「築古の建物では評価額が下がり、既存の建物を活かしてリノベーションした場合は、税負担が軽くなる傾向があります。実例としては、新築時に年間約15万円だった固定資産税が、築20年で年間10万円を切る程度まで下がったケースもあります。新築すれば再び評価額がリセットされて税額も上昇するため、リノベーションの方がお得ともいえます」
新築とリノベ、どちらを選ぶべきか?

――結局、新築とリノベーションのどちらを選べばよいのでしょうか?
正田「お客様からよく聞かれるのが、『この家は本当に安全に直せるのか?』『予算的に収まるのか?』『そもそも残すべき価値があるのか?』といった問いです。特に古民家などの場合、“壊していいのかどうか”で悩まれる方が多いです。判断の出発点となるのは「建物の状態」です。耐震性が確保できるか、傾きや雨漏りがないか、シロアリ被害がないか。これらを専門家が調査し、安全性に問題がないと判断できれば、リノベーションは十分に検討できます。直そうと思えば、江戸時代の建物であっても骨組みを残して再生することは可能です。ただし大切なのは“コストとの兼ね合い”です。どれほど古い家でも、直すための費用が生活設計に見合わなければ意味がありません」
――コストについて考える際、どんな基準を持ったら良いでしょうか?
正田「リノベーションのコストを考えるには、家族構成や将来のライフプランも重要な判断材料です。例えば「子育て世代でこれから家族が増える」「将来はコンパクトな暮らしに移行したい」といったビジョンによっても、選ぶべき方向は変わります。昔の家は広すぎることが多いので、“減築”という選択肢を提案することもあります。離れや蔵を整理し、必要な母屋だけを残す。こうすることで維持費も抑えられ、無理なく暮らし続けることができます。大切なのは、どうやって家を直すか?というハード面の話だけでなく、どんな暮らし方をしていくのか?というソフト面をしっかり相談に乗ってくれるプロと出会うことです」
まとめ
新築とリノベーション、それぞれに明確なメリット・デメリットがあり、どちらが正解というものではありません。大切なのは「建物の状態」「予算」「将来の暮らし方」という3つの視点をもとに、安心して長く暮らせる選択肢を見極めることです。そして、その判断には専門的な知識と経験が欠かせません。では、実際にどのような会社に相談すれば良いのか?次回は「信頼できる依頼先の見極め方」と「なんば建築工房ならではの強み」について、さらに深掘りしてご紹介します。