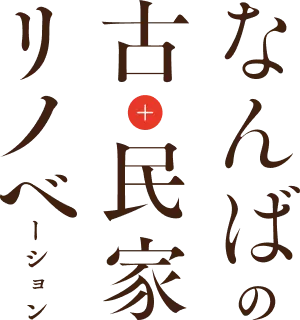古民家鑑定士とは?専門資格が支える“本物の古民家リノベーション”

〜 岡山・倉敷で安心して古民家リノベーションを任せられる施工会社をお探しの方へ〜
古民家鑑定士とは、どんな資格?

——古民家鑑定士とは、どのような資格なのでしょうか?
正田「古民家鑑定士とは、簡単に言えば“古民家専門のホームインスペクション(住宅診断)のプロ”です。昭和25年以前に建てられた、いわゆる“伝統構法の古民家”は、現代の建築基準とは構造が大きく異なります。特に“石場建て”と呼ばれる、地面に置かれた石の上に直接木造の構造体を載せる構法や、柱と梁で構成された柔構造のつくりは、現代の住宅に使われるような耐力面材を使ったガチガチの剛構造とは正反対の考え方なんです。そうした建物を現代の耐震基準で評価すると、“倒壊の恐れあり”というような、実情に合わない結果が出てしまうことも少なくありません。」
——古民家には古民家に合った診断基準が必要、ということですね。
正田「その通りです。だからこそ、2009年に古民家再生協会によって、全国的な資格制度として古民家鑑定士という仕組みをつくったんです。この資格では、古民家の特性を正しく理解し、適切な調査と評価ができる人材を育成しています。資格取得者は今では全国に約2万名、岡山県にも約260名ほど在籍しています(2025年現在)。実際の調査では、約600項目にわたって詳細な評価を行い、建物の構造的な状態、耐久性、改修の可否や優先順位などを総合的に判断するのが古民家鑑定士の仕事です。」
古民家鑑定士が行う、古民家総合鑑定とは?

——どのような方が古民家鑑定を依頼されるんでしょうか?
正田「依頼される方はさまざまですが、特に多いのは、これから古民家を購入しようと検討している方や、すでに所有していてリノベーションや売却を考えている方ですね。古民家って、外観だけでは状態がわからないことが多いんです。構造の中身まで見ないと、修理ができるのか、どこまで手を入れればよいのかが判断できません。購入後に“思ったより傷んでいて直せない”“予算をはるかに超える修繕費がかかる”というケースも実際にあるので、そういった事態を避けるためにも、購入前の段階でしっかり鑑定しておくことが本当に大切です。例えば、古民家を購入した後に『これ、直せません』と分かっても、私たちもどうにもならないというのが正直なところです。」
——600項目というのは、具体的にどのような内容を調査するのでしょうか?
正田「調査項目は多岐にわたりますが、大きく分けると8つのカテゴリに整理されています。
【古民家鑑定の評価項目】
1. 周辺環境適法性
2. 環境性能
3. 構造躯体
4. 屋根
5. 外壁
6. 基礎
7. 内部
8. 予防保全計画
周辺環境や地盤の状況、建物の構造躯体(柱や梁などの基本骨組み)、屋根・外壁・基礎などの外装部分の劣化状況、それから内部空間の状態や使い勝手、設備の更新状況なども確認します。また、環境性能といって、自然素材が使われているか、建材に有害物質がないかなどもチェックします。さらに、予防保全計画という視点で、今後どのくらいの頻度でメンテナンスが必要になるか、維持管理の見通しまで評価します。それぞれのカテゴリで評価された情報は、八角形のレーダーチャートに可視化され、6段階の総合評価とともに古民家鑑定書として提出されます。お客様にとっても、視覚的にわかりやすい資料になりますし、判断材料として非常に有効なんです。」
【古民家鑑定の結果】
1. 残念ながら再生は難しいようです
2. 伝統資材買い取りでの解体が可能です
3. 伝統資材の再活用が可能です
4. コストがかかりますが再生可能です
5. 再生移築が可能です
6. 現状のまま維持可能です
正田「下に行くほど評価が高くなります。ご依頼いただいた中で一番多いケースは、”4. コストがかかりますが再生可能です“と評価されたものですね。」
——古民家の鑑定は、実際にどのような形で行われるのでしょうか?
正田「古民家総合鑑定と言って、より精度の高い調査を行うために、古民家鑑定士に加えて、床下調査の専門家(全国床下インスペクション協会所属)や、伝統構法に特化した耐震診断を行う“伝統再築士”といった別分野の専門家と協力して、三者で総合的な鑑定を行います。耐震診断では、実際に建物の揺れ方を計測するため、微動センサーを使って南北・東西方向の微細な振動を測定します。その結果をもとに、耐震性を高めるためのダンパーの設置位置や数を決定し、実際に設置後、再測定して性能が改善されたかどうかも確認します。最近では、岡山の林原美術館の東蔵のリノベーション工事でこの手法を採用しました。」
古民家鑑定士が在籍している安心感

—— 古民家鑑定士が在籍している会社と、一般的なリフォーム会社との違いは?
正田「鑑定を受けた古民家については、要件を満たせば『フラット35』の融資対象になったり、『リフォーム瑕疵保険』をかけることもできます。これらの制度は、古民家再生協会に加盟している施工会社でないと適用できないもので、信頼できる古民家専門の事業者に相談するメリットのひとつです。」
正田「また、一番大きな違いは、“古民家という建物の成り立ちと構造を理解しているかどうか”だと思います。ありがちなのは、柱や梁をすべて壁やボードで隠してしまい、見た目だけ新しく仕上げて“古民家再生しました”と言ってしまう施工です。しかし、それは表面的な化粧直しにすぎず、構造躯体の状態や本来の意匠を無視している場合が多いです。たとえば、差し鴨居といって、構造上重要な部材を“お客様の希望で頭がぶつかるから切ってほしい”と言われて、何も考えずに切ってしまう工務店もあります。でもそこは実は構造躯体の一部で、切ってしまうと建物全体の強度に大きな影響が出る。こうした見えない部分まで把握して設計・施工にあたるのが、本当の意味で古民家に向き合っている施工会社だと思います。」
なんば建築工房の古民家”性能向上リノベーション”

——なんば建築工房として、古民家リノベーションで大切にしていることは?
正田「私たちが目指しているのは、“性能向上リノベーション”と“日本の住文化の継承”の両立です。古民家は『寒い・暗い・使いにくい』といった三大不満を抱えがちですが、それらを現代の技術で解消しつつ、断熱性能や耐震性能をしっかり確保して、快適に暮らせる住まいにアップデートする。その上で、古民家の建築文化、たとえば、昔の家は地域の公共事業であったという“普請と結”の考え方や、地域に根ざしたつくりの工夫、自然素材の活かし方などを次世代につなげていきたいと思っています。実際、私たちは全国古民家再生協会のネットワークの中で多くの先進事例や手法に触れながら、自社に合った方法を常にアップデートしています。これまで培ってきた職人の技術や経験をベースに、伝統を活かしながら、安心・安全で魅力ある古民家の再生を目指していきたいですね。」
古民家リノベーションについてのお問い合わせ
お問い合わせフォームより、お気軽にお問い合わせください。
または資料請求ページより、古民家再生の事例が載ったパンフレットをお届けいたします。