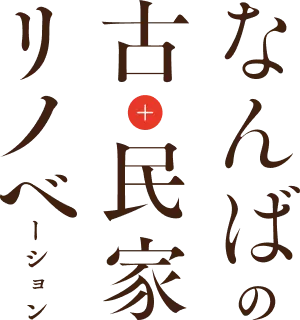Vol.17 プランづくりのツボ(現地チェック)

プランづくりを始める前に欠かせないのが、現地訪問。
現地を見る際に、どんなところを見ているのか、どんな家づくりが理想なのかを語ります。
四代目主人・難波 恭一郎のインタビューです。
2016年頃の古い映像ですが、参考資料として公開いたします。
文字起こしは意訳を含みます。ぜひ動画もお楽しみください。
[赤字] インタビュアー
[黒字] 難波会長
現地に行かれて、まず一番にどんなところからチェックされますか?
「お客様がどのような家を望まれているか」をまず一番に聞きますね。ざくっというと和か洋か。それから和であれば重たい和なのか、数奇屋と呼ばれる軽い和なのか。洋は洋で、近代的な洋なのかもっと昔の明治とか大正とかというような洋なのか、ゴシックのようなもうひとつ昔の洋なのか。まず外観のイメージ、それから内部がどういう部屋がお好きかをまず一番に聞き取ります。
次に大事なのは10年後、20年後その家がどうなるか。人数が増えるのか減るのかにもよって、大きさが違ってくるじゃないですか。多くの方は現状の人数に合わせて家づくりをしますが、20年も経過すると子どもが家を巣立って、それなのに、自分が年をとると大きな部屋がいくつも空いている、というような家になってしまいます。なので、10年後、20年後というのを10年単位くらいで考えて、家はご提案していくというところ。そこから始まります。
最近相談があった中で、「とりあえず現地を見に来てください」という風なケースもありましたか?
あります。現地を見てまず考えるのが、「その町に溶け込むかどうか」ということ。その家だけが特有に浮いてしまういうのも僕はおかしいと思うんですね。周りに溶け込むかどうか、それから、近所の家がどういう配列になっているか、どちらからの目線を気をつけないといけないかというのを見ます。そして、平屋なのか二階なのか、窓はどこについているのか、そういった大まかなことはチェックして帰りますね。
それから、当然寸法がありますので、隣の家がどのくらい高さで、窓がこういう風についているというのを、だいたい頭に入れて、メモして帰りますね。
まわりの風景に溶け込むことが大事というのは、どういうことですか?
私は、他と違うことを強調して、これ見よがしに「どうだ私はこういう家を建てたんだ」、というのはあまり好きじゃないんです。それよりも、座ってじっと見たときに、たとえば柱一本あるべきところに、柱がない。でも普通は気がつかない。けれど、柱がないからものすごくすっきりしている。それがプロの目から見たときには分かってくれる、そういうものを作りたいんですね。
そこには必ず職人としての技術が入っているんです。柱一本抜くがために、そういう技術を見せないような形で、職人の手による特殊な木組みをしている。素人ならすっきりしているな、だけかもしれないが、プロが見たら一目で分かります。これは屋根の天井の下とか、屋根へ隠しているなと。ものすごくすっきりしているなと。プロが誉めてくれるというかね、そういうイメージで。
一般の方向けには、派手な家がいいのかもしれません。たとえば、玄関入ってすぐそばに大きな柱がどんとあるとか。玄関入ったところなんかは普通は壁があるわけで、そこに大きな太い柱はないんですけど、これ見よがしに柱を入れる。普通はそうじゃなくて、そこから中に入った、大きな広間にある、家の中央にあるものが大黒柱なんです。重要なところだから太い柱を使っている、それが自然なわけですよね。それを、これ見よがしに太い柱を入れるというのは、これは邪道だと。やはりあるべきところに柱があり、あるべきところに梁があるべきです。
職人でないとできない家というのがありますが、それをなんとなしに設計の中に入れこんで、それをどうだ、私はこんだけ出来るんだぞ、と言うんじゃなくて、家に入っていただいて、そのうちお客さんがそれに気づいてくれる。そんな家が良いですね。必ず入った人は気づきます、最終的にはね。
そうすると、なんばさん、人が言ってたんだけど、ここは柱がいるんですね、梁が太いのが必要なのに、ものすごく小さく見せてますね、というような評価が返ってきます。 ああ、なんばさんのところはすごいな、と。