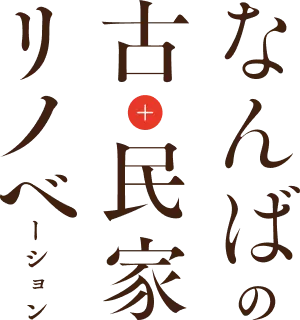倉敷・下津井の古民家リノベーション~通り土間の魅力と活用方法~

岡山で古民家鑑定士インストラクターを務めているなんば建築工房の正田です。今回は古民家の町屋と通り土間のこのについてお話いたします。
古民家の中には、現代住宅にはない独特の構造や暮らしの知恵が詰まっています。倉敷市下津井で行った建物調査では、職住一体の町屋づくりと「通り土間」という空間が印象的でした。今回はその魅力と、古民家リフォームでの活用方法をご紹介します。
町屋づくりと通り土間の歴史
下津井の旧道では、建物がひしめき合いながら並ぶ町屋づくりが見受けられます。昔の古民家は、店舗や作業場と住居が一体化した「職住一体」の形が一般的で、街道沿いの建物は「ウナギの寝床」と呼ばれる間口が狭く奥行きの長い造りになっていました。
これは、かつて建物の間口の広さで税金が決まっていたことや、限られた敷地を有効活用するための知恵です。しかし奥まで光や風が届きにくくなるため、坪庭や通り土間を設けて採光や通風を確保していました。
実例紹介|通り土間を活かす古民家リノベーション
今回調査した築およそ100年の古民家も、通り土間を抜けて奥の住居へとアプローチする構造でした。土間部分はかつて作業場や店舗として使われ、通り土間は風や光を通す役割も果たしていました。
現代の古民家リフォームでは、この通り土間を活かしてカフェの客席やアトリエ、ギャラリースペースにする事例も増えています。各地域の町屋は観光客向け店舗や移住者の拠点として再生されるケースも多く、空き家活用の成功例となっています。
今回の町屋古民家も、表ではお店があり奥に住居がある典型的な町屋づくりでした。このようなつくりの古民家で大切なポイントをご紹介します。

古民家再生で大切なポイント
1. 耐震補強と断熱改修の両立
築50年〜100年以上の古民家は、現行の耐震基準を満たしていないことが多く、大地震時の安全性が課題となります。特に土壁造や伝統構法の建物は、地震時の揺れ方が現代建築とは異なるため、構造を理解したうえでの補強計画が不可欠です。
耐震補強だけでなく、冬の寒さや夏の暑さを軽減する断熱改修も同時に行うことで、快適性と省エネ性を高められます。例えば今回の例でいうと、通り土間に面する壁や天井部分に高性能断熱材を施工しつつ、開口部は部屋内に断熱性の高い内窓サッシを活用すると、外部の意匠を損なわず断熱性を上げることが出来ます。
これにより、歴史ある外観を守りながら現代的な暮らしやすさを実現できます。
※古民家再生総合調査
2. 古材活用で雰囲気を継承
古民家リノベの大きな魅力は、長い年月を経て味わいを増した梁、柱、建具などの古材が持つ独特の風合いです。新しい材料では再現できない質感や色合いは、空間全体の印象を引き締めます。
例えば、通り土間の天井に太い梁を見せることで、訪れる人に歴史の重みと温かみを感じてもらえます。また、古い建具をカフェの入口ドアや間仕切りとして再利用すれば、コスト削減とデザイン性向上を同時に実現可能です。古材を適切に再生・加工して使うことで、古民家の個性を残しつつ新しい価値を生み出すことができます。
※古材ギャラリー
3. 用途に応じた動線設計
通り土間はもともと、表から裏まで人や荷物を通すための通路であり、作業場としても使われてきました。現代のリノベーションでは、この長い空間をどのように活用するかがポイントです。
例えば、店舗リノベーションなら、通り土間を奥の客席や中庭へと誘導する“回遊性のある導線”にすることで、訪れる人のワクワク感を演出できます。宿泊施設なら、通り土間をラウンジや共用スペースとして設計し、ゲスト同士の交流の場にするのも効果的です。
動線計画を工夫することで、歴史的な構造を活かしながらも、現代のライフスタイルや商業用途にマッチした空間へと変えることができます。
当社のお家でも、店舗とまではいきませんが一般住宅で通り土間を取り入れた事例もありますのでご参考にして下さい。
※通り土間のあるレトロ和風住宅/岡山市北区
古民家の通り土間は、単なる通路ではなく、風や光を通し、人や物をつなぐ暮らしの知恵の結晶です。なんば建築工房では、岡山県(岡山市・倉敷市・玉野市・総社市・備前市・瀬戸内市・備前市・赤磐市・和気町・吉備中央町・高梁市・井原市・浅口市・笠岡市・井原市・高梁市)を中心に古民家リフォームや空き家活用に豊富な実績があります。
歴史を活かした暮らしや店舗づくりをお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。
※古民家鑑定士と巡るショールームツアー